倒れている人をみたら 心肺蘇生の手順
感染防止のために
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日々の生活の中で多くの不安を抱えていらっしゃることと思います。 いざというとき、応急手当を行う方の感染を防止するため、以下の点に気をつけてください。
- 自分のマスクがあれば着用しましょう。
- 意識や呼吸の確認は、倒れている人の顔と応急手当を行う方の顔があまり近づきすぎないようにします。
呼吸の確認は、胸とお腹の動きを見て行います。 - 胸骨圧迫を開始する前に、倒れている人の口と鼻に、布やタオル、マスクなどがあればかぶせましょう。
- 応急手当を行う方が複数いれば、一人は部屋の窓を開けたりして、室内の換気をしましょう。
胸骨圧迫のみを行い、人工呼吸は行わないでください。
人工呼吸の訓練を受けており、それを行う意思がある家族等は、胸骨圧迫に加えて人工呼吸を行います。
人工呼吸用マウスピース(一方向弁付)等があれば、活用しましょう。
- 口元にかぶせた布やタオル、マスクなどは、直接触れないようにして廃棄しましょう。
- 石けんを使い、手と顔をしっかり洗いましょう。
- うがいをしましょう。
119番通報後、救急隊が到着するまでの間に、災害救急情報センター勤務員や救急隊員が電話でアドバイスをすることがあります。
AEDの装着と使用については、これまでどおり変更はありません。
これらの対応は、新型コロナウイルス感染症流行期の対応です。
JRC(日本版)ガイドライン2020の公表を受け、東京消防庁では、令和4年12月1日から、新しいガイドラインに基づく応急手当の講習を開始しました。
1. 肩をやさしくたたきながら大声で呼びかける

2. 反応がない場合、反応があるかどうか迷った場合
又はわからなかった場合は、大声で応援を求め、119番通報とAED搬送を依頼する

3. 呼吸を確認する

4. 普段どおりの呼吸がない場合、判断に迷う又はわからない場合は、すぐに胸骨圧迫を30回行う
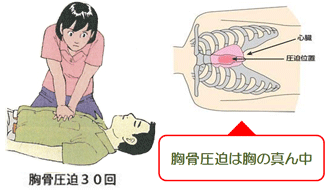
5. 訓練を積み技術と意思がある場合は、胸骨圧迫の後、人工呼吸を2回行う
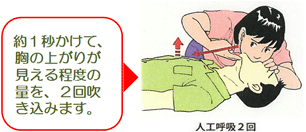
- 人工呼吸の方法を訓練していない場合
- 人工呼吸用マウスピース等がない場合
- 血液や嘔吐物などにより感染危険がある場合
人工呼吸を行わず、胸骨圧迫続けます。
人工呼吸用マウスピース等を使用しなくても感染危険は極めて低いといわれていますが、感染防止の観点から、人工呼吸用マウスピース等を使用したほうがより安全です。
胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を繰り返して行います。
6. AEDが到着したら
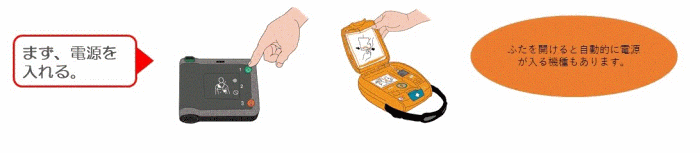
7. 電極パッドを胸に貼る
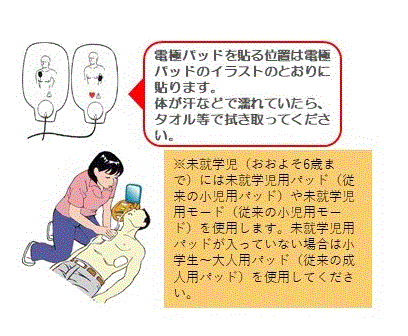
8. 電気ショックの必要性は、AEDが判断する。
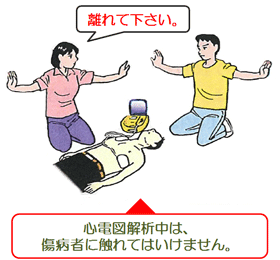
9. ショックボタンを押す
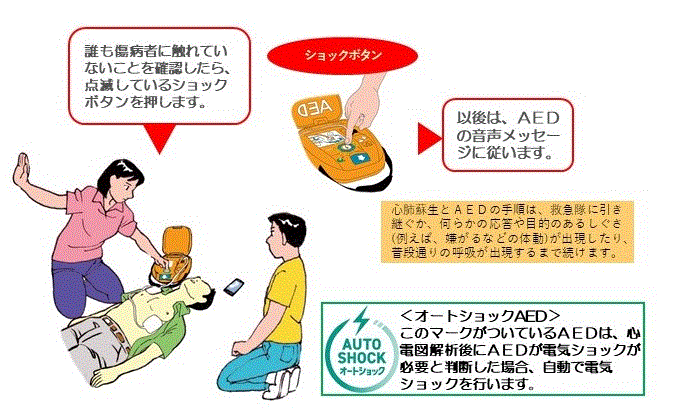

新しいガイドラインに基づき改正されたのは下の表のとおりです。
令和4年12月1日改正
| 改正前 救急蘇生法の指針(2015)に準拠 | 改正後 救急蘇生法の指針(2020)に準拠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通報 | 反応がないと判断した場合、又は反応があるかどうか迷った場合には、直ちに大声で助けを求め、119番通報とAEDの搬送を依頼する。 | 反応がない場合、反応があるかどうか迷った場合又はわからなかった場合は、大声で応援を求め、119番通報とAED搬送を依頼する。 | |||||
| 胸骨圧迫 開始の判断 | 普段どおりの呼吸が見られない場合、又はその判断に自信が持てない場合は胸骨圧迫を開始する。 | 普段どおりの呼吸がない場合、判断に迷う又はわからない場合は胸骨圧迫を開始する。 | |||||
| AED | 小学生以上 | 成人用モード又は成人用パッド | 小学生以上 | 小学生から大人用モード 又は小学生から大人用パッド |
|||
| 小学生未満 | 小児用モード又は小児用パッド | 小学生未満 | 未就学児用モード 又は未就学児用パッド |
||||
救命の可能性と時間経過
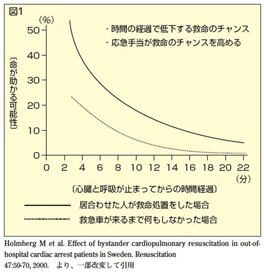
救命の可能性は時間とともに低下しますが、救急車が到着するまでの間、居合わせた人が応急手当を行うことにより、救命の可能性が高くなります。
心肺蘇生のまとめ
| 胸骨圧迫 | 位置 | 胸骨の下半分 (目安は胸の真ん中) |
|---|---|---|
| 方法 | 両手 小児:両手又は片手 乳児:指2本 |
|
| 深さ |
約5cm (小児・乳児は胸の約3分の1) |
|
| テンポ | 100回~120回/分 | |
| 人工呼吸 | 量 | 胸の上がりが見える程度 |
| 時間 | 約1秒 | |
| 回数 | 2回 |
胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせは30:2
応急手当の方法は、さまざまな研究や検証を重ね、原則5年に1度、より良い方法へ改正されています。新たな応急手当の方法は、それまでの方法を否定するものではありません。大切なことは、目の前に倒れている人を救うために「自分ができることを行う」ことです。
緊急の事態に遭遇したときに適切な応急手当ができるように、日頃から応急手当を学び、身につけておきましょう。
問合せ先
- 救急指導課

