ぼやと大火
最新の情報ではありませんので、あらかじめご了承ください。
明暦の大火(明暦3年)、目黒行人坂の火災(明和9年)、丙寅の火災(文化3年)を江戸三大大火と呼んでいます。
一般的には大規模な火災あるいは広域にわたって多くの家屋を焼いた火災を大火と呼んでいますが、具体的に大火の定義があるわけではありません。
明治14(1881)年、東京帝国大学(後の東京大学)の『理科会粋・第三帙』に、江戸・東京の大火を総合的に分析研究した結果を発表した、山川健次郎氏(後に東京帝国大学総長を二代務めた)の論文によると、「火元から焼けどまりまでの間に直線を引き、長さ15町(約1,635メートル)以上に達したものを大火と呼ぶことにする」とし、これに該当した93件の火災を大火と名付けています。
一方、損害保険料率算定会の『大火調査資料』(昭和29年発行)では、大火の定義の困難性を指摘しながらも、結果的には焼失建物50戸以上の火災を、一応の大火の基準として調査対象としています。
昭和26(1951)年4月23日に、国家消防庁(現在の総務省消防庁)消防研究所技術課長と同庁管理局総務課長の連名で出された「大火災の動態調査報告方について」では、「焼失面積が3千坪(約1万平方メートル)以上の火災」と指定しながらも、「2千坪(約6,600平方メートル)以下のものでも通常『大火』と呼ばれるものに準用する」としています。
今日、大火の基準らしきものとしては、『消防白書』の資料欄に掲載されている昭和21(1946)年以降の大火があり、その注に「大火とは、建物の焼失面積が33,000平方メートル以上の火災をいう」と書かれています。
ただし、これにしても、あくまでも資料として選出するために便宜上定めた基準です。
江戸の大火の傾向を見てみますと、太平洋側気候区にあって、次のような気象条件のときに大火が起こっています。
(1) 冬から春先に北ないし北西の冷たい季節風(からっ風)が吹き続け、長い間にわたって降雨がない場合
(2) 春先又は秋口、日本海を通る強い低気圧のため南風(春一番)が吹く場合
前記の山川氏の研究でも、7、8月には1件の大火もなく、9月から月を追うごとに1件、2件、4件、7件と増え、正月は12件、2月は19件となり、3月には26件とピークに達しています(明暦の大火は正月18日ですが、太陽暦では3月に当たる)。4月以降は13件、8件、1件と急速に減少していきます。
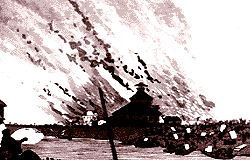
歴史に残る大火(戦争火災は除く)を挙げると、江戸時代は明暦の大火になります。
明治時代には明治14(1881)年1月26日に神田区松枝町から出火して、東神田から日本橋馬喰町を焼きつくし、さらに本所深川にまで延焼して、15,000余戸を焼失した火災が最も大きな火災です。
大正時代はいうまでもなく、関東大地震により東京市と横浜市でそれぞれ大火が発生し、大被害を受けました。
昭和時代に入ってからの最も大きな火災は、昭和9(1934)年3月21日に発生した函館市の大火です。
これにより400万平方メートル余を焼失して、死者2千余人、焼失戸数2万余戸という大損害を受けました。
外国の大火として有名なものには、64年のローマの大火(皇帝ネロによる放火説がある)、1666年9月2日にロウディンランのパン屋から出火したロンドンの大火、米国の防火週間を生み出す契機となった1871年のシカゴの大火、1906年4月18日未明、マグニチュード8.3の大地震がサンフランシスコを襲ったとき発生したサンフランシスコの大火などがあり、このほか、聖書に語られているソドムとゴモラの大火があります。
<>大火の反対語として被害の少ない火災をぼやと呼び、昭和45(1970)年までは、小火の字を当てていました。民俗学者である柳田国男氏は、著書『火の昔』の中で、「小火(もやともいう)は、もともとたきつけにするような細い木の枝に、すすきや笹のまじったものの呼び名で、これらが燃え上がる様を形容していわれるようになったものであろう」と述べています。
また、火事のごく小さいのを小火と呼ぶのは「気のきいた江戸っ子のものの言い方で、小さくてすんだという喜びに形容に、こんな言葉を持ってきて、笑わせたのがはじめだろうと思います」と付け加えています。
現在ぼやは、火災の焼損程度を4つに区分するものの一つとして使われていますが、他に全焼、半焼、部分焼があります。

