消防ヘリ患者搬送第一号は高校生
最新の情報ではありませんので、あらかじめご了承ください。

「空飛ぶ消防隊」として活躍している東京消防庁航空隊は、建築物が高層化するなど時代の変化を的確にとらえた新たな救助対策等として、昭和41(1966)年11月1日に全国の消防機関に先駆けて設置され、翌昭和42(1967)年4月1日に第一号機アルエットⅢ型の「ちどり号」をもって業務を開始しました。 これが航空消防のはじまりです。
消防ヘリコプターは上空からの消火、人命の救助、災害状況の把握、重傷救急患者の高度医療機関への搬送、物資の緊急輸送など幅広く活用されています。
東京消防庁の消防ヘリコプターによる患者搬送の第一号は、大島町の高校三年生で、通学途中に交通事故にあい、重傷のため地元診療所では処置ができず、都立墨東病院まで搬送したものです。
これは航空業務を開始した年の昭和42年10月14日のことでした。
また、山林火災での初の消火活動は、昭和44(1969)年5月6日の西多摩郡雲取山での火災でしたが、このころには二号機「ひばり号」が就航していました。 その後、複雑多様化する災害事象に的確に対応するため、漸次増強されました。
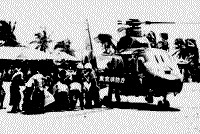
海外で初めて日本の消防ヘリコプターが活躍したのは、平成3年5月、大型サイクロン(台風)に襲われたバングラデシュで、死者が13万人を超えた災害でした。
このとき、国際消防救助隊とともに派遣されたのは、東京消防庁の「かもめ号」と大阪市消防局の「おおさか三号」(いずれも14人乗り)で、機体を解体してジャンボ機に積み、5月16日成田空港から空輸されました。
現地における2機の総飛行回数は112回、総飛行時間は93時間10分で、救援輸送に活躍したことから、現地の人びとから「平和の象徴」「赤い神様」と呼ばれました。
一方、国内の災害では、平成5年7月12日、焼損家屋300戸、倒壊家屋805戸、死者202人、行方不明29人、傷者305人の被害が発生した北海道南西沖地震に、消防応援隊として、東京消防庁の「つばめ号」「ひばり号」「ゆりかもめ号」の3機のヘリコプターが派遣されました。
現地での3機の総飛行回数は60回、総飛行時間は68時間35分で、情報収集(被害状況の確認)、救援輸送に活躍しました。
また、平成7年1月17日、神戸市、芦屋市、西宮市、淡路島を中心に、甚大な被害をもたらした阪神・淡路大震災でも、消防応援隊として、東京消防庁のヘリコプター「ゆりかもめ号」「ちどり号」「ひばり号」「かもめ号」「つばめ号」「はくちょう号」の各機が派遣されました。

現地での6機の総飛行回数は139回、総飛行時間は235時間30分に及び、情報収集(被害状況の確認)や救援輸送に活躍しました。
平成6年9月12日、ヘリコプターによる林野火災の消火活動、山岳事故の救助活動、島しょ地域の救急患者搬送等を迅速に行うため、立川広域防災基地内に「東京消防庁多摩航空センター」を開設しました。

