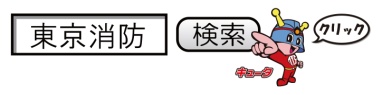第8章 身近な危険と安全への備え
- 身の回りの事故……キッズ団員
- 第8章 身近な危険と安全へのそなえ……ジュニア団員
- 第6章 日常生活の事故防止……高校生団員
この章の趣旨
- 生活の中の「身近な危険」を学び、自ら事故防止ができるよう意識させる。
- また、友達や兄弟等に注意ができることを目標とする。
| 基本科目 | 指導内容 | 達成目標 |
|---|---|---|
| 防火・防災 |
|
キッズ団員用カリキュラム
|
ジュニア団員用カリキュラム
|
||
高校生準指導者用カリキュラム
|
東京消防庁では、日常生活の中で起きる様々な事故により救急搬送された事案を分析し、その特徴と予防のポイントについて、都民に注意喚起をしています。
指導者ハンドブックでは、消防少年団員の世代に多い事故を取り上げます。
最新の情報については、東京消防庁のホームページで調べましょう。
1 小学生に多い事故
小学生世代は、活動が活発化し、自分でできることも増えていきます。しかし、自立していく一方で、危険を避けるための知識は十分とは言えません。
ここであげる事故防止のポイントは、一例です。大きな事故が起きないように、事故防止のポイントをキッズ・ジュニア団員が理解し、自ら実践できるように指導していきましょう。
(1)公園で安全に遊ぶ
子供達が楽しく遊ぶ公園の遊具で、事故が起きています。小学生の事故は、子供達だけで遊んでいるときに多く発生しており、小学校低学年の児童で最も多く発生しています。
遊具別に発生件数をみると、滑り台が最も多く、次いで、ぶらんこ、ジャングルジム、鉄棒、複合遊具、うんていとなっています。遊具で遊ぶときには、次の決まりを守って遊ぶこと、また、友達や他の子供達に注意喚起できることを目標としましょう。
- 周りで遊んでいる小さな子供に気を付ける。
- 自分の年齢にあった遊具で遊ぶ。
- カバン、ランドセル、マフラー、フードなどが、滑り台などの手すりに引っ掛かり首に巻きついてしまうという事故が起きている。遊ぶ時の服装に注意する。
- 上着の首回り、ズボンや上着のすその紐、靴紐などが引っかからないように結んでおく。靴はしっかり履く。
(2)はさまれる事故
エスカレーター

エスカレーターに、サンダルや長靴が巻き込まれて足を受傷する事故が起きています。エスカレーターでは次の決まりを守り、事故防止に努めましょう。
- ベルトで遊んだり、ベルトにまたがったりしない。
- 手すりにつかまり、黄色い線の内側に乗る。
- 歩かない、走らない、逆走しない。
- 小さい子供と乗る時は、手をつなぐ。
ドア

電車などの自動ドアや玄関の扉などの手動ドアで事故が発生し、指を切断してしまうような大きな事故につながることがあります。ドアの開閉時には、自分自身も他の人もケガをしないように注意しましょう。
- ドアに手をつかない。
- ドアを閉めるときには、人がいないか確認してから閉める。
シャッター
学校やビル、ガレージなどに設置されている電動式のシャッターに身体を挟まれて、大ケガを負ったり死亡したりする事故が発生しています。
- シャッターが閉まり始めた時には、近寄らずにシャッターから離れ、無理に下をくぐるようなことはしない。
- シャッターで遊んだり、自動操作盤をいたずらしない。
(3)自転車事故(警視庁「なくそう子供の交通事故!!」より)
子供(幼児、小学生、中学生)の交通事故は、自転車乗車中に最も多く発生しています。自転車に乗るときは、交通ルールを守りましょう。
自転車は、車道通行が原則です。
- 子供(13歳未満)が自転車に乗るときは、歩道を走ることができます。
大人(13歳以上)が自転車で歩道を走れるのは、標識などがある場合と車道を通るのが危険な場合です。ただし70歳以上の人と身体の不自由な人も、子供と同じように歩道を通ることができます。
歩道では、車道寄りをゆっくり進みましょう。
- 歩行者が多いときは、自転車から降りて、押して歩きましょう。
交通ルールを守りましょう。~自分、そして他の人を守るために~
- 二人乗りをしてはいけません。
- 自転車で並んで走ることはやめましょう。
- まわりが暗くなったら、かならずライトをつけましょう。
- 信号を守りましょう。
- 「止まれ」の標識があるところは一度止まって、右と左の安全を確認しましょう。
ヘルメットをしっかりかぶりましょう。
(4)高所からの転落・墜落
マンション等の天窓やガラス屋根の上に乗って遊んだり、ボールを取りに行って天窓に乗ったりして、転落や墜落する事故が起きています。また、ベランダやマンションの外階段で遊んでいて、転落や墜落する事故も起きています。
高所からの転落や墜落は、大きなケガを負うことも多く、時には死に至ることもある重大な事故となっています。日常の生活空間ですが、転落や墜落の危険があることを十分に理解させる必要があります。


2 中高生に多い事故
(1)スポーツ時のケガ
中学・高校生は、比較的日常生活の事故の発生が少ない世代です。しかし、人に接触する、ボールにぶつかる等、スポーツ時にケガをすることが多い傾向にあります。
こんな事故が起きています
転落した事例
- 少年野球の練習中、建物の屋根(約3m)に上がったボールを取りに行き、誤って転落した。【重篤】
ぶつかった事例
- サッカーの試合中に右大腿部が相手選手の膝とぶつかり、動けなくなった。【中等症】
事故を防ぐために
- ウォーミングアップやストレッチは入念に。
- お互いに、普段の練習や競技の前には事故防止の注意喚起を行うとともに不測の事態に備え、応急手当、AED(自動体外式除細動器)の使用方法等を確実に身に付けることが必要です。
(2)歩きスマホは危険です!!
駅、道路などで、歩きながらや自転車に乗りながら、携帯電話、スマートフォンやタブレット端末などを操作していて、事故に遭い、救急搬送されています。
人や物に「ぶつかる」、「転ぶ」、階段やホーム等から「落ちる」などの事故により、重症を負った方もいます。
こんな事故が起きています
ぶつかった事例
- 飲酒後帰宅途中に携帯電話を操作しながら足早に歩行していて、柱に衝突して受傷した。【軽症】
- スマートフォンを見ながら信号機のない道路を横断しようとしたところ、走ってきた乗用車と接触し受傷した。【軽症】
転んだ事例
- 携帯電話を見ながら歩いていて、マンション前の階段で転倒し、背部を受傷した。【軽症】
- 路上で歩きながらスマートフォンを操作していた際、路上の段差に躓いて転倒し、右肩を受傷した。【軽症】
落ちた事例
- 屋外階段をスマートフォンを見ながら降りていたところ、足を滑らせ6、7段の高さから転落し、右足部を受傷した。【軽症】
- 駅のホーム内でスマートフォンを操作しながら歩行中に、誤って線路に転落し受傷した。【中等症】

事故を防ぐために
- 歩行中や自転車で走行中に携帯電話やスマートフォン等を操作したり、画面を見ることは、周りが見えなくなり大変危険です。また、通話時にも事故は発生しています。立ち止まって安全な場所で行いましょう。
- 携帯電話やスマートフォン等を使用しながら運転している自転車と接触し受傷する事故も発生しています。歩行中や自転車で走行中は、自分自身がケガをするだけでなく、周囲の人にケガをさせたりする等、迷惑をかけているということを認識しましょう。
- 自転車を運転中の携帯電話やスマートフォン等の使用は禁止されています。
(3)エアゾール缶使用時の引火事故に注意
エアゾール缶を使用した際に、何らかの火源に引火した事故により、救急搬送される事案が発生しています。
エアゾール製品は、ヘアスプレー、ムース、デオドラント、シェービングクリーム、冷却スプレー、殺虫剤などに広く使用されています。
こんな事故が起きています。
ガスに引火した事故
- 密閉された自家用車内で冷却スプレーを自身の体に噴射し、その後、車内でたばこに火をつけようとしたところ、ライターの火が滞留した可燃性ガスに引火し受傷した。【重症】
- ガスコンロのつまりを取るために、エアーダスターを使用してすぐガスコンロを点火したところ、滞留していたガスに炎が引火し、左手を受傷した。【重症】
- ガスコンロに火をつけて調理しながらシンクで制汗剤のスプレー缶を噴射してガス抜きを行っていたところ、ガスコンロの炎がスプレー缶のガスに引火し炎が一瞬燃え上がり、両腕を受傷した。【軽症】
事故を防ぐために
エアゾール缶には、LPGなどの可燃性ガスが噴射剤として使われている製品が多くあります。
- 使用する際は、炎に向けたり、炎や火気の近くで使用したりしてはいけません。
- 直接火に向けてスプレーをしなくても、服に残ったガスなどに引火する可能性があります。
- 火気を使用している室内で、大量に使用してはいけません。
- 製品に書かれた注意事項に従い、正しく使いましょう。
火のそばで、エアゾール缶に穴を開けるのは、とても危険です!!

エアゾール缶使用時の禁止事項
- 火の中に絶対に入れない
缶は密封されているので、たとえ空になったと思われるものでも破裂する危険があります。 - 火気注意
火気を使用している室内で使用しないでください。炎の近くで使用しないでください。 - ファンヒーター、暖房機のそばには置かない
火気の付近に置かないでください。破裂の危険があります。 - 電磁調理器上で使用、保管しない
電源が間違って入ってしまった場合、カセットボンベ等が過熱し、破裂する危険があります。 - 40℃以上になるところに置かない
直射日光の当たる窓の付近では40℃以上になる事がありますので、置かないでください。 - 自動車の窓近くに置かない
夏季の自動車内では、長時間のうちに缶が過熱され、破裂する危険があります。
問合せ先
- 防災安全課